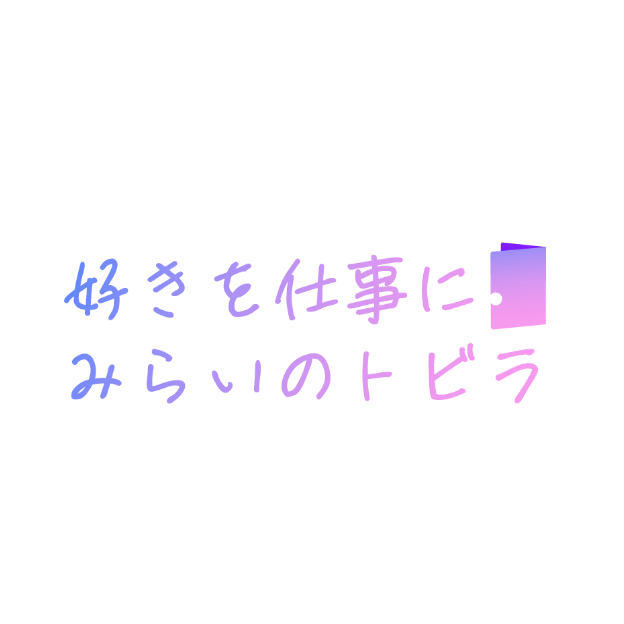医療秘書の仕事についてわかる!
三幸学園は毎週オープンキャンパスを実施中!
職業・業界や進路に関する質問にもお答えします。
医療秘書の仕事とは?
病院などの医療機関で、医師や看護婦をはじめとした医療スタッフのサポート、また大学病院などにおいては教授が行う研究などのサポートと言ったような、医療機関における裏方の事務仕事を担当するのが、医療秘書の主な仕事内容です。
似たような仕事として、医療事務の仕事がありますが、主に受付事務や会計などと言ったように、直接患者さんと接することで病院と患者さんの橋渡しをする医療事務の仕事とは異なり、実際の医療秘書の仕事において、患者さんと接して仕事をする機会は、あまり多くありません。 今回は医療秘書の仕事の内容や、医療秘書に必要となる資格を解説します。医療秘書を目指している方は、ぜひ今回の記事を参考に、最短で医療秘書になることを目指してみてください。
医療秘書になるために資格は必要?
医療秘書という仕事に就くためには、国家試験合格と言ったような免許・資格を持っている必要はありません。
しかし、一般的な事務やコンピューターの資格だけでなく、1級から3級まである医療秘書技能検定などは、民間資格とは言え医療秘書のスキルを証明するためには有効です。
自分の持っているスキルや知識を証明することができるので、医療秘書技能検定の資格を持っていることは就職や転職には有利と言えます。
学歴に関しては、医療秘書として働く医療機関にもよりますが、一般的には仕事を始める際に大学卒業などと言ったような、学歴を問われる職業ではありません。 しかし、専門学校などで医療秘書に関するコースを受講している人は、実際に仕事をした際のスキルだけでなく、必要な医療用語などを使う機会も多いので、就職をする際にも有利と言えます。
医療秘書の待遇やお給料
医療秘書のお給料は、他の一般的な事務職と同等程度ということが多いようです。
公的機関や大学病院などで正社員として働く場合には、ボーナスなども規定に従って支給されます。
勤務条件などに関しては、働く職場が、個人の病院か公的機関なのかなどによっても異なってきます。
医師や看護婦さらには病院スタッフのサポートに回ることが多い仕事なので、大学病院など大きな医療機関で働く医療秘書のなかには、担当する職員や教授などと一緒に出張に同行する機会が多い場合もあります。 大学病院などで働く医療秘書の場合には、学会などの資料作りのサポートによる残業や、出張の動向に伴う出張手当が支給されることで、年収が平均以上となる場合もあります。
医療秘書として働くために必要なこととは?
一般の企業などと同様に、コンピューターや事務処理能力と言ったような、秘書として最低限必要なスキルは求められます。
一般的な事務処理能力以外にも、人とのコミュニケーション力やマナー、さらには一般常識といったものは医療秘書として働くために最低限持っている必要があります。
また、事務能力以外にもある程度の医学や医療の知識などを持っていると、実際に仕事をしていく上で医療用語などの専門用語を使う機会が多くても、戸惑うことがありません。
専門学校に通い医療秘書の勉強をしている人は、医療秘書としての医療現場で使われる、専門用語にも慣れることができるというメリットがあります。
医療秘書として実際に仕事を始める前に、医学的な知識を身につけることもできれば、仕事をする上でとても有利です。 医療秘書という仕事は、医師や看護婦と立場は違いますが、病院などにおいて医療現場を後方から支えるという、とても大切な役割を担う仕事と言えます。
医療秘書になるなら三幸学園
三幸学園では医療秘書を始めとする医療関係の仕事に特化したコースを多く用意しています。
三幸学園は資格・就職サポートが充実しており、高い合格率・就職率となっています。
まずはお近くの学校の資料やオープンキャンパスで情報をご確認ください。