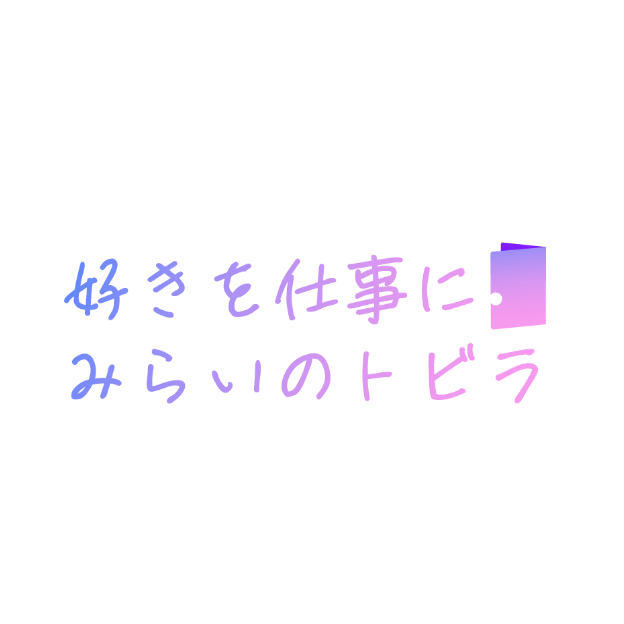社会福祉士
「社会福祉士」とはどのような仕事か知っているでしょうか。この記事では社会福祉士の仕事内容や給与や年収、将来性、なるためにはどうすればいいのかなどについて紹介しています。社会福祉士に興味のある人や、社会貢献できる仕事を考えている人は、ぜひ読んでみてください。
三幸学園は毎週オープン キャンパスを開催中!職業・業界や進路に関する質問にもお答えします!
【目次】
社会福祉士の仕事内容
社会福祉士とは、「社会福祉士及び介護福祉士法」の第二条にもとづく、国家資格を有する人になります。
社会福祉士の仕事は、身体的や肉体的、または高齢などの理由で日常生活を送ることが難しい人に対して、福祉の面で問題を解決するために働くことです。
さまざまな理由で日常生活が困難な人の相談に乗ったり、助言をしたり、福祉サービスや医療機関と連携して、相談者が自立できるようにサポートします。もし介護施設に就職した場合は、社会福祉士自身が、介護スタッフを兼任して働くこともあるでしょう。
出典|参照:社会福祉士及び介護福祉士法|e-Gov法令検索サイト
社会福祉士の支援対象
社会福祉士の支援対象は、身体または精神的な障がいがある人や、環境的な理由で日常生活を送ることが困難になっている人です。このため支援対象になる人は幅広く、高齢者や障がい者だけでなく、低所得者や子どもも含まれるでしょう。
社会福祉士が働く施設もさまざまで、医療機関や介護施設、福祉施設や行政、教育現場などがあります。
介護福祉士との違い
社会福祉士と介護福祉士は、それぞれ仕事内容が異なっている他に、必要になる資格にも違いがあります。
社会福祉士は日常生活を送ることが困難な人を、自立できるようサポートします。相談者の相談に乗ったり、助言したりすることが主な仕事内容です。
介護福祉士は、要介護者に対して介護サービスを提供することが仕事になります。要介護者の日常生活を直接サポートすることが仕事なため、体力を要する仕事とよく言われているでしょう。
社会福祉士も介護福祉士も、どちらも国家資格です。しかし介護福祉士の資格は学歴に関係なく受験できるのに対して、社会福祉士は福祉系の大学や短期大学、養成施設などで課程を修了していなければなりません。
出典|参照:社会福祉士及び介護福祉士法|e-Gov法令検索サイト
社会福祉士の就職先は?
社会福祉士の資格を活かすことができる就職先は、医療分野や児童分野、教育分野や高齢者分野、障がい者分野など幅広くなっています。
たとえば、医療分野では病院やクリニックなどが就職先になるでしょう。児童分野に進んだ場合は、養護施設や児童養護施設、乳児院や児童相談所、母子生活支援施設などが対象です。
教育分野では学校、高齢者分野では介護老人福祉施設や在宅介護支援センターなどの就職先があります。
社会福祉士の将来性
社会福祉士に将来性はあるのか、気になっている人もいるでしょう。社会福祉士の仕事は現在需要が高まっており、今後も需要は拡大していくと予想されているため、将来性に期待がもてると考えられています。
これは、高齢化が進む日本では高齢者施設が増え続けていることや、児童のサポートを行うスクールソーシャルワーカーの需要が増えていることなどが理由でしょう。とくに高齢化の問題は、すぐには解決しない問題です。
また医療施設や刑務所などといった施設でも、社会福祉士の需要は増えてきています。
社会福祉士の給与・年収
社会福祉振興・試験センターが令和2年度に実施した「就労状況調査」によると、社会福祉士や介護福祉士、精神保健福祉士の平均年収は約403万円です。
「就労状況調査」に参加した人のうち、男性は約2万6千人で平均年収は約473万円、女性は約5万2千人で平均年収は約365万円でした。
また雇用形態は正規社員がもっとも多く約81.6%、次がパートタイム職員で9.3%、契約社員約8.4%となっています。派遣社員は約0.2%でした。
出典|参照:社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の「就労状況調査」(速報版)について|社会福祉振興・試験センター
社会福祉士になるためには
社会福祉士になるためにはどうしたらいいのか、必要な資格と勉強などを紹介します。
社会福祉士は、独学のみではなることのできない職業です。目指す場合はどういった進路で進んでいくのか考え、必要な勉強をしておきましょう。
国家資格を取得する
社会福祉士になるには「社会福祉士」の国家資格が必要なため、資格取得を目指しましょう。そのためには、まず社会福祉士になるための「社会福祉士国家試験」の受験資格を得なければなりません。
受験資格を得る方法は、条件の組み合わせによって11通りあります。たとえば福祉系大学で指定科目または基礎科目を履修し、大学で学んだ年数と相談援助実務経験の年数を合わせて4年を超えていると、受験資格が得られるでしょう。
福祉系大学に通わなくても、社会福祉士養成機関に通った上で相談援助実務経験を2年積んだり、一般大学で学び相談実務経験と合わせて4年を超えたりしていれば、受験資格を得られます。相談実務経験のみで4年を超えている場合も、受験可能です。
受験資格を得て「社会福祉士国家試験」を受け、合格すれば、社会福祉士資格を取得できます。
出典|参照:社会福祉士国家試験|公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
出典|参照:社会福祉士及び介護福祉士法|e-Gov法令検索サイト
社会福祉士試験の受験科目
社会福祉士試験には、これらの受験科目があります。
・人体の構造や機能及び疾病
・心理学理論及び心理的支援
・社会理論及び社会システム
・現代社会と福祉について
・地域福祉の理論や方法
・福祉行財政及び福祉計画
・社会保障について
・障がい者への支援や障がい者自立支援制度について
・低所得者への支援や生活保護制度について
・保健医療サービス
・権利擁護と成年後見制度
・社会調査の基礎
・相談援助の基盤と専門職、理論と方法
・福祉サービスの組織や経営
・高齢者に対する支援や介護保険制度
・児童や家庭への支援と福祉制度
・就労支援サービス
・更生保護制度
人体や心理学、社会保障の各制度、高齢者・障がい者・児童・低所得者への支援、利用可能な制度の知識といった、幅広い内容が対象となっていることが特徴です。
出典|参照:社会福祉士国家試験|公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
社会福祉士に向いている人の特徴
社会福祉士に向いているのは、より良い社会を実現したい人や知らない人でも相談をきちんと聞いてあげられる人、常に学んでいける人などでしょう。
社会福祉士は、何らかの事情で日常生活が困難になった人たちへ関わり、問題を解決して自立していけるようにサポートする仕事です。介護問題や児童虐待、いじめといった問題にも関わるため、相手の立場になって考えられる、思いやりのある人が求められます。
仕事の中で、知らない人の相談を受ける機会もあるでしょう。相手が誰であっても、辛抱強く話しを聞いてあげられる人が向いています。
また社会福祉士が関わる法律や制度は時代に合わせて変わっていくため、自分の仕事に関することを学び続けられる人が向いているのです。
まとめ
社会福祉士は、社会全体の問題に直面することの多い仕事です。多様な問題を抱える現在の日本では社会福祉士の需要は高く、今後も必要とされる場が増えるのではないかと考えられています。
ただし、社会福祉士になるには試験に合格し、国家資格を得なければなりません。社会福祉士を目指す人は、どうやって資格取得を目指すのか進路を考え、一歩を踏み出していきましょう。