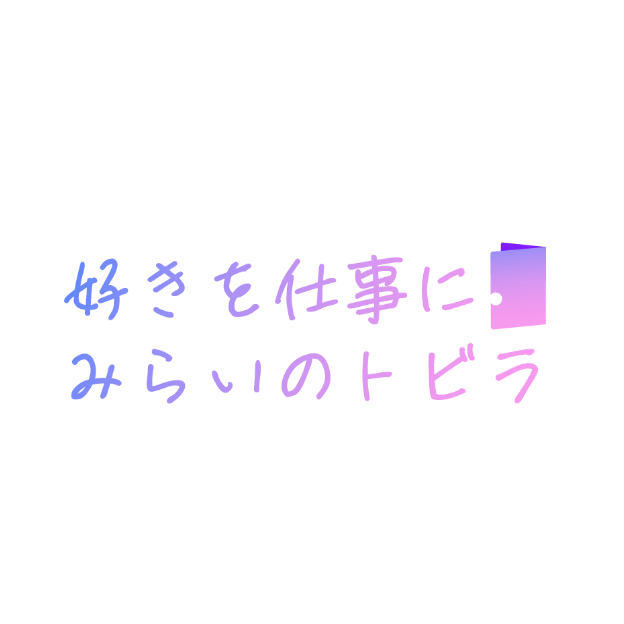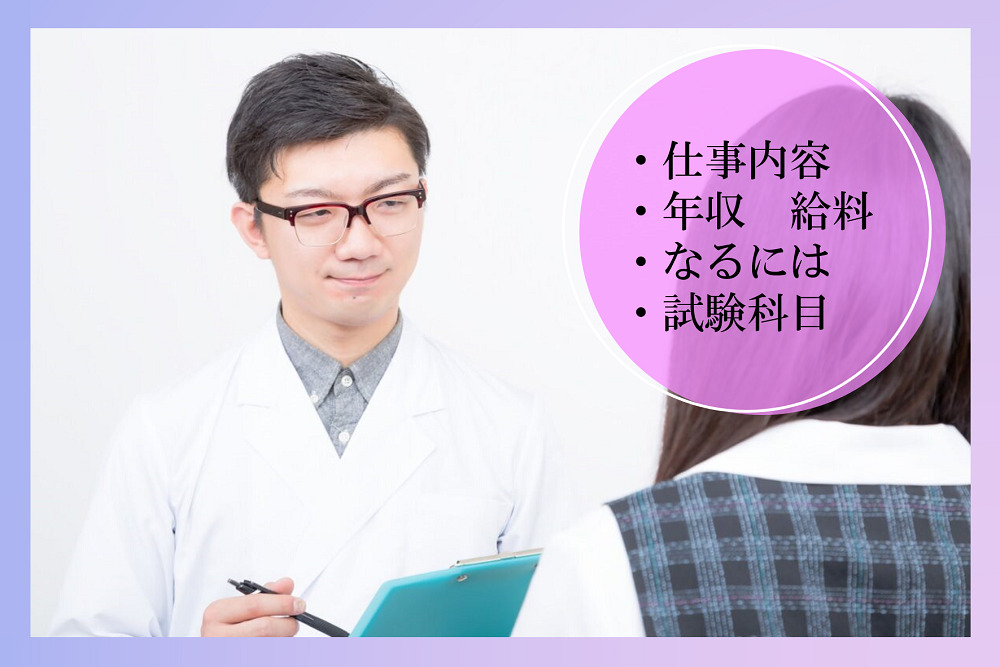
精神保健福祉士の仕事内容についてわかる!必要なスキルや年収は?
「精神保健福祉士」という仕事をご存知でしょうか。この記事では、精神保健福祉士の詳しい仕事内容や、給与・年収のほか、この仕事に就くためのルートを紹介しています。精神保健福祉士に興味がある方や、進路選択の参考にしたいという方は、ぜひ、この記事を読んでみてください。
三幸学園は毎週オープン キャンパスを実施中!
職業・業界や進路に関する質問にもお答えします。
【目次】
精神保健福祉士とは?
「精神保健福祉士」とは、「精神保健福祉士法」にもとづく国家資格を有する人です。精神保健福祉分野の専門家として、精神科領域を担当する「ソーシャルワーカー」となります。
主に精神障がいを持った方やその家族に対して、専門的な知識や訓練で支援し、必要な手続きを行うなど、日常生活を送るためのサポートをします。
社会福祉士との違い
「社会福祉士」は、「社会福祉士及び介護福祉士法」にもとづいた国家資格です。精神保健福祉士と同じソーシャルワーカーですが、社会福祉士との主な違いは、「支援する対象」です。
精神保健福祉士が精神障がいを持った方や、その家族を支援するのに対し、社会福祉士は心身の障がいにかかわらず、低所得や家庭の事情など、様々な境遇の方を支援します。
社会福祉士が支援する対象は高齢者から子どもまで幅広く、高齢者や障がい者向けの介護施設、児童相談所などで勤務しています。
臨床心理士との違い
「臨床心理士」は国家資格ではなく、日本臨床心理士資格認定協会という公益財団法人が認定した「民間資格」です。
仕事内容にも以下のような違いがあるため、チェックしておきましょう。
まず、精神保健福祉士の仕事内容は、日常生活の支援や病院の退院や就労などに必要な手続き、相談者に適した施設・サービスの紹介などです。
一方、臨床心理士の仕事内容は、心理検査やカウンセリング等の臨床心理技法によって相談者の心の問題を中心に解決することです。
つまり、心の問題を解決するのが臨床心理士、心の問題によって引き起こされる日常生活の困難などを支援するのが精神保健福祉士といえるでしょう。
精神保健福祉士の仕事内容をご紹介
精神保健福祉士は、医療・障害者福祉・行政など、様々な分野で活躍しています。
ここからは、各分野でどのような仕事をしているのか、詳しく見ていきましょう。それぞれの仕事内容を把握し、進路を選択する際の参考にしてみてください。
医療に関する仕事
主な勤務先は精神科病院や総合病院の精神科、クリニック、訪問看護ステーションなどです。
精神科ソーシャルワーカーとして、患者の受診や退院の手続き、退院後の社会復帰のため支援機関と連携するなどのサポートを行います。
福祉に関する仕事
福祉に関する仕事では、生活介護事業所、ケアホーム、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、地域活動支援センター、介護施設など幅広い勤務先が挙げられます。
また、福祉関連の場合、勤務先によって精神保健福祉士としての仕事内容が異なります。
たとえば、自立訓練事業所では日常生活の動作をサポートし、就労移行支援事業所では、就職に関する支援やアドバイスをすることが主な仕事です。
行政に関する仕事
行政に関する仕事では、各役所や保健所、市町村の保健センター・精神保健福祉センターなどで働くことが多く、支援事業に関わる手続きなどが主な仕事になるでしょう。
具体的な仕事としては、地域ネットワークの構築や、就労支援事業や地域移行支援活動の分析・将来計画の立案などが挙げられます。そのほか、住民への啓発活動など、幅広い視点で精神障害者の支援を考えていきます。
精神保健福祉士の給与
2019年に実施した精神保健福祉士就労状況調査では、精神保健福祉士の平均年収は約404万円でした。それ以前の調査では約347万円だったため、前回に比べて平均年収は上昇しています。
雇用形態の割合は、正規職員が最も多く約80.6%、次いでパートタイムが約9.5%、契約職員が約9.2%、そして派遣職員が約0.2%という内訳になっています。
精神保育福祉士の将来性
現在、精神障がいを持った方への支援は、入院医療を主軸としたものから、地域生活を主軸としたものにシフトしています。
それに伴い、精神保健福祉士が必要とされる領域も幅が広くなってきました。福祉や行政、教育機関におけるニーズも増え、一般企業においてもメンタルヘルスケアが注目され始めています。
適切な医療や福祉のサービスなど、専門的な知見を持っている精神保健福祉士は、今後さらに様々な業界・分野におけるニーズが高まっていくでしょう。
精神保健福祉士になるには?
精神保健福祉士は、国家資格です。そのため、精神保健福祉士の国家試験を受験するにあたっては、厚生労働大臣が指定する基礎科目、または指定科目の履修が必須となります。
場合によっては、相談援助の実務経験や養成施設の修了が必要です。
精神保育福祉士になるためのルート
保健福祉系大学の場合は、2~4年制で指定の科目を勉強することで受験資格が得られます。2年制・3年制の場合は、卒業後に相談援助の実務を行う必要があるため注意しましょう。
短期で取得する場合は、保険福祉系大学卒業後に短期養成施設で半年間勉強し、受験資格を得る方法もあります。
なお、既に社会福祉士の資格を持っている場合は、大学に入り直す必要はありません。短期養成施設で半年間勉強することで、受験資格を得られます。
一般大学の場合は、大学卒業後に一般養成施設で1年以上勉強した後に受験資格を得られますが、2年制・3年制の場合は卒業後に相談援助の実務経験を積んだ後、一般養成施設に入る必要があります。
相談援助の実務経験が4年ある場合は、そのまま一般養成施設へいくことが可能です。
精神保育福祉士国家資格について
精神保健福祉士の国家試験は、1年に1回実施されています。9月上旬〜10月上旬に願書を提出し、2月上旬に試験、3月上旬に合格発表という流れです。
試験は、例年17科目から全163問出題され、1問につき1点の配点です。合格基準は総得点の約60%であり、すべての科目群で得点する必要があります。
これまで、精神保健福祉士の合格率は約60%前後で推移してきましたが、2023年・2024年の試験では約70%台に上がっています。
社会福祉士の合格率が約30〜60%のため、精神保健福祉士の合格率は高いといえるでしょう。
試験科目
第27回試験より、新しい出題基準が適用される予定です。以下でその内訳を見てみましょう。(2024年05月現在)
専門科目
・精神医学と精神医療
・現代の精神保健の課題と支援
・精神保健福祉の原理
・ソーシャルワークの理論と方法(専門)
・精神障がいとリハビリテーション論
・精神保健福祉制度論
共通科目
・医学概論
・心理学と心理的支援
・社会学と社会システム
・社会福祉の原理と政策
・社会保障
・権利擁護を支える法制度
・地域福祉と包括的支援体制
・障がい者福祉
・刑事司法と福祉
・ソーシャルワークの基盤と専門職
・ソーシャルワークの理論と方法
・社会福祉調査の基礎
なお、登録申請中を含む社会福祉士の登録者については、共通科目が免除されます。
まとめ
精神保健福祉士は、精神障がいを持った方だけではなく、現代のストレス社会を生きる人々にとって必要なケアやサポートができる専門家です。今後も様々な分野で必要とされる職業になるでしょう。
精神保健福祉士になるには、指定された科目を勉強し、試験に合格することが必要です。これから精神保健福祉士を目指す方は、どの学校で学ぶかをしっかり検討し、これからの進路を考えていきましょう。