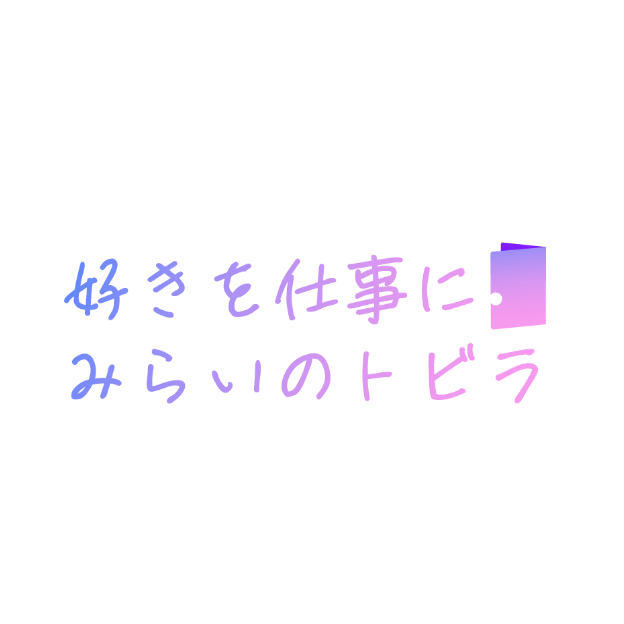ベビーシッター
ベビーシッターになりたいけれど、どうすればベビーシッターになれるのか分からず、困っている人はいませんか。
この記事を読むことで、ベビーシッターの仕事内容や資格の必要性、ベビーシッターになるために必要な勉強について知ることができます。
ベビーシッターに興味のある方は、ぜひこちらを読んでみてください。
【目次】
ベビーシッターとは
ベビーシッターとは、保護者の代わりに赤ちゃんや子どものお世話をしてくれる人です。ほかには、チャイルドシッターや乳幼児シッターと呼ばれることもあります。
ベビーシッターがお世話をする対象は、0歳から12歳が一般的です。そのため、お世話の内容は赤ちゃんのおむつ替えやミルクの世話にとどまらず、子どもと一緒に遊ぶことや食事の用意することも含む場合があります。
ベビーシッターの仕事内容
ベビーシッターの仕事内容は、保護者からの依頼により、子どもの日常生活のお世話をすることです。具体的には、食事やおやつの補助、着替え、入浴、遊び、寝かし付けなどを安全に留意しながら行います。
また、保育園・習い事への送迎や病児保育、家事の代行など、依頼者の希望に沿った内容で対応することが必要です。
ベビーシッターになるには
ベビーシッターになるには、特別な資格や免許はいりません。ベビーシッターになることを決めれば、だれでも目指せる職業です。
1人で子どものお世話をするベビーシッターは、子どもの人格形成において大切な役割を担うことになります。そのため、大学や専門学校などで子どもの発達や健康について、基本的な知識を身に付けることが理想的と言えるでしょう。
学校に通う
保護者に安心して子どもを預けてもらうためには、子どもの保育や教育についての知識が必要です。知識の習得手段として、短大や4年制大学の保育学科、幼児教育学科などへ進学するほか、保育や幼児教育が学べる専門学校へ入学する方法もあるでしょう。
また、通学が難しい場合は通信制課程の利用も可能です。
ベビーシッターサービスページに登録する
ベビーシッターサービスには、ベビーシッター専門の派遣会社やマッチングサービスがあります。
派遣会社の場合、自分のスキルにあった仕事を紹介してもらえるのが大きなメリットでしょう。マッチングサービスは数時間からフルタイムなど、自分で働く時間を設定できることが多く、自由に働けるメリットがあります。
資格をとる
ベビーシッターとして信用を高めるためには、保育士資格や幼稚園教諭免許の取得があります。ほかには、日本能力開発推進協会(JADP)のベビーシッター資格、公益社団法人全国保育サービス協会(ACSA)の認定ベビーシッター資格があります。
保育関連の資格を取得することにより、保護者から保育のプロとして認識されて、安心して子どもを預けてもらえるでしょう。
ベビーシッターが向いている人の特徴
ベビーシッターに向いている人には、どのような特徴があるでしょう。ベビーシッター向きである人は、人の面倒を見るのが得意であったりコミュニケーション能力が高かったりします。
ここからは、ベビーシッターに向いている人の特徴をくわしく紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
面倒見がいい人
困っている人を見ると放っておけない、頼られることが力になるなど面倒見がいい人はベビーシッターに向いています。
子どもの急な体調不良、保育所や学校の学級閉鎖などは、働くパパやママを困らせる出来事です。困っているパパやママ、子どもたちを放っておけない人はベビーシッターにピッタリでしょう。
コミュニケーション力が高い人
話す能力が高い人はベビーシッターの適性があると言えます。ベビーシッターの仕事は、保護者の不安に寄り添うことのため、信頼関係が大切です。
コミュニケーションをしっかりとることで、子どもとの安心感や保護者との信頼感を高めていきましょう。
責任感がある人
1人で子どものお世話をするベビーシッターは、子どもの命を1人で預かっている状態です。子どもは、大人が想像できないような危険なことをする場合があります。
また、ベビーシッターの業務中は、留守宅の見守りを任されている状況でもあります。そのような中で、責任感を持ち、子どもの安全を1番に考えて行動してくれる人であれば、安心して子どもと家を預けられるでしょう。
家族のように子どもと接せられる
ベビーシッターは入浴の補助や寝かしつけを行うこともあるため、子どもにとっては親に代わってお世話をしてくれる人になるでしょう。
そのため、子どもに対して愛情を持って、家族のように接することのできる人はベビーシッターに向いています。
ベビーシッターのやりがい
ベビーシッターには、どんなやりがいがあるでしょう。困っているパパやママ、子どもたちのサポートをする救世主とも言えるこの仕事には、たくさんのやりがいがあります。
ベビーシッターのやりがいについて紹介します。ぜひ、参考にしてみてください。
子どもの成長を見守れる
ベビーシッターは指名制や定期契約などで、同じ子どものお世話をすることがあります。
訪問を重ねるうちに、言葉が上手になっていく様子を一緒に近くで見守れたり、前回はできなかったことができるようになっていく姿を見られたりするのは、ベビーシッターならではのやりがいです。
子どもひとりひとりに寄り添える
保育園や幼稚園では集団行動を学べるメリットがありますが、子どもひとりひとりに対応できる時間が限られています。
それに対して、ベビーシッターは個別保育がメインのため、子どもの個性に合わせた対応が可能です。時には、子どもの得意なことや興味のあることを見つけるきっかけを作ってあげられるでしょう。
保護者の方から直接感謝を言われる
ベビーシッターとして子どもを預かる場合、保護者とコミュニケーションをとることになります。そして、ベビーシッターを依頼する保護者は、仕事を休めなかったり、子どもの預け先がなかったり困っている場合がほとんどでしょう。
保護者の方と話す機会が多いベビーシッターは、直接感謝の言葉をかけてもらえる機会が多く、やりがいになります。
ベビーシッターの働き方
ベビーシッターは、利用者からの依頼を受注して仕事をします。給料体系は、毎月同じ給料の固定給制の正社員よりも、働いた分が収入になる時間給制が一般的です。
また、派遣登録やマッチングサービスでの働き方では、自分に合ったタイミングで働くことができます。そのため、扶養範囲内での勤務や午後の数時間のみといった働き方が可能でしょう。
ベビーシッターの主な勤務先
ベビーシッターの勤務先は、依頼者が指定する場所です。主に勤務する場所は、依頼者の自宅ですが、ホテルや託児スペースが勤務先となる場合もあります。
ここからは勤務先別に紹介していきます。
依頼者の家
ベビーシッターの主な勤務先は、依頼者の自宅です。自宅での保育は、依頼者が送迎する手間がなく、子どもが慣れた場所のため、安心して過ごせるメリットがあります。
また、勤務先が個人宅のため、立ち入り不可の場所や使用不可なものについて、事前に確認が必要です。
託児スペース
託児スペースが置かれている場所は、商業施設内にあるキッズスペース、コンサートやイベント時のみに運営されるスペースなどがあります。そのほか、映画館やホテルなど、多くの場所で需要があります。
上記ような託児スペースでは「買い物の時間だけ」「コンサートの時間だけ」など、短時間での依頼が特徴的です。
ホテル
一部のホテルでは託児ルームが完備されており、ディナーや子どもが参加できないアクティビティ時に一時的に利用することが可能です。また、結婚式の際にはベビーシッターが数時間子どもの面倒を見るサービスや、客室での託児も行われます。
個人開業
ベビーシッターは、個人で開業することができます。開業の際は、ベビーシッターの資格があると信用が高まるため、資格取得がおすすめです。
また、開業の場合は自宅を託児スペースとして利用することで、訪問以外での勤務が可能になります。ただし、自宅に子どもを預かるために必要なものを用意しておく必要があるでしょう。
ベビーシッターが自分に向いているかよく考えよう
ベビーシッターの仕事は、待機児童が多い日本では子育てのサポートとして需要が高まる可能性のある仕事です。働く時間や場所についても自由度が高く、子ども好きであれば、魅力的な仕事でしょう。
しかし、1人で子どもを預かるベビーシッターには、必要な知識が多くあります。また、子どもに対する責任感も求められるため、子どもが好きだという理由だけで目指すのは難しいでしょう。
本記事を読んで、自分がベビーシッターに向いているかよく考え、ベビーシッターを目指してみましょう。