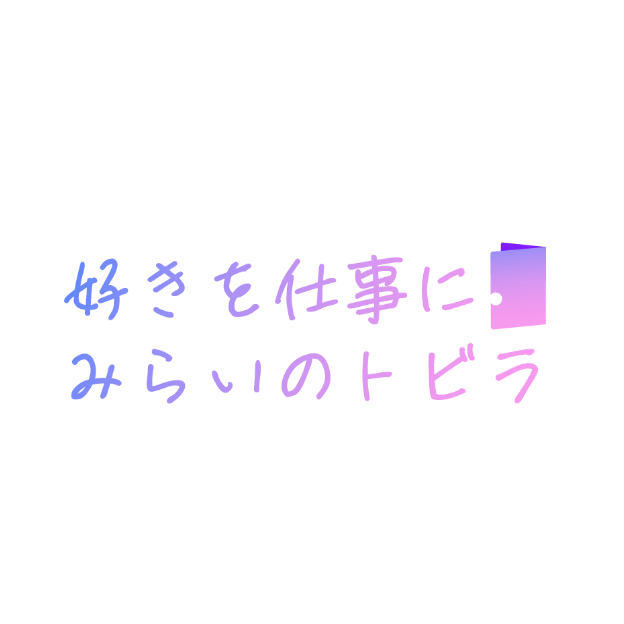地方公務員の仕事内容についてわかる!必要なスキルや年収は?
この記事では地方公務員の仕事内容や適正、やりがいについて紹介しています。また、採用試験の概要や勉強の仕方、平均的な給料月額も知ることができます。
地方公務員に興味のある方は、ぜひこちらを参考にしてください。
【目次】
地方公務員とは
地方公務員とは、地域を運営する都道府県や市町村などの地方公共団体で働く公務員のことを指します。公務員全体の80%以上となる約280万人が地方公務員です。
都道府県庁や市役所の職員をはじめ、警察官や消防士、公立学校の教員も地方公務員も地方公務員です。他にも公立病院、上下水道、交通、公営企業などに勤務している人も地方公務員に含まれます。
地方公務員と国家公務員の違い
公務員の中で地方の公務に従事する者を地方公務員、国の公務に従事する者を国家公務員といいます。地方公務員が行うのは自治体の住民サービスなど、国家公務員が行うのは国全体に関わる業務です。
どちらも日本国憲法において「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定められています。
地方公務員の仕事内容
地方公務員の仕事内容は、安定した住民サービスの維持向上や安全、秩序の確保、インフラの整備などです。一般行政以外に警察や消防、上下水道など、多岐にわたります。
ここからはさまざまな仕事のうち、ごく一部ですが、詳しくみていきましょう。
市役所などで事務(行政職)

市役所では地域住民の生活に密着した仕事を行います。市役所の仕事として思い浮かべるのは、住民票や戸籍の管理やマイナンバー関連業務、地方税に関わる事務といったものがあるでしょう。
他にも、医療介護や福祉サービス、公立学校の運営や保育園の入所、ゴミの収集なども市役所の仕事です。仕事の分野は多岐にわたります。
建築や農業(技術職)
地方公務員の主な技術職として、土木職と農業土木職の2つからなる総合土木職があります。
道路や堤防などの整備や維持管理、都市計画など公共土木事業を行うのが、土木職です。農業土木職は、食料を安定供給するための農業農村整備事業や、自然災害発生時に農地などを復旧するための災害復旧事業を行います。
警察官や消防士(公安職)

警察官や消防員などの公安職も地方公務員に位置づけられています。
都道府県の警察組織に所属し公共の安全と秩序を守るのが、警察官の大きな役割です。警察には次のような6つの職種があります。
・生活安全警察
・地域警察
・刑事警察
・交通警察
・警備警察
・総務・警務警察
消防士は、火災や交通事故、自然災害などの現場で、消火活動や人命救助を行います。現場や病院へ搬送中の救急車内で、救護行為や特定医療行為を行うためには、救急救命士の資格が必要です。
心理判定(心理職)

地方公務員の心理職は心理学や社会福祉の専門的な知識を活かして、相談者やその家庭が抱える問題を解決するために心理判定を行ったり、適切な支援を提案したりする仕事です。
主な職場として、児童相談所や障がい者施設、精神保健福祉施設、教育相談機関などがあります。
地方公務員は市町村と都道府県どちらが良い?
都道府県と市町村における地方公務員の仕事内容の大きな違いの一つは、住民との距離です。
都道府県の仕事は広域行政といわれており、国と市町村の仲介や民間企業に対する窓口が主な業務で、住民と直接関わる機会はほとんどありません。一方、市町村の仕事は住民との関わりが深い住民サービスがメインです。
国や企業など大きな組織と仕事がしたいのであれば都道府県、住民との関わりにやりがいを見出すのであれば市町村が向いているといえるでしょう。
地方公務員になるには地方公務員試験が必要
地方公務員になるためには、地方公務員試験に合格する必要があります。ここからは地方公務員試験がどのようなものなのか、難易度や合格率について詳しくみていきましょう。
また、地方公務員試験に合格するための対策や勉強方法についても紹介します。
地方公務員試験とは
地方公務員試験には、次のような多くの種類があります。一部を除き、ほとんどで大学卒業程度の学歴が受験資格として必要です。
・地方上級(行政職)
・地方上級(心理職)
・地方上級(福祉職)
・地方上級(技術職)
・市役所
・地方初級
・民間企業経験者採用試験
・警察官採用試験
・消防官採用試験
目指す職種に合った試験を受けましょう。
地方公務員試験の難易度・合格率
公務員試験の難易度は職種や自治体によっても変わりますが、一般的に難易度は高めです。合格率は全体で見ると15%~20%程度で、容易に受かる試験とはいえないでしょう。
理由として、試験範囲が広いことや採用人数が決まっていること、また、採用試験であるため、筆記試験の結果だけでなく面接試験の内容も加味されることなどがあげられます。
地方公務員試験に受かるには
地方公務員試験は出題範囲が広く、出題数も多いので、勉強する範囲を明確にした上で日ごとに設定し、効率よく勉強をしていきましょう。
出題の多い科目から取り組むことも大切です。教養科目では文章理解と数的処理、専門科目では憲法や民法、経済原論からの出題が多いので、先に取り組むようにすることがおすすめです。また、出題傾向の把握や知識定着のために、過去問を繰り返し解くことも効果的でしょう。
地方公務員になる4つのメリット

地方公務員は安定した職業というイメージはあるけれど、具体的なメリットについてはわからないという人も多いのではないでしょうか。ここからは、地方公務員になる4つのメリットについて、紹介していきます。
自身が考える条件にあっているかどうかの参考にしてみてください。
安定した収入
平均年収は、民間企業よりも地方公務員の方が高い水準にあります。
また、地方公務員の給与は年功序列で上がっていくので、安定した収入を得られ、将来設計が立てやすいでしょう。
福利厚生が手厚い
地方公務員は、福利厚生の手厚さが魅力です。給与と別に支給される手当や各種祝金や見舞金、弔慰金などの一時金も充実しています。
民間企業よりも多く設定されている年間休暇の他に、有給休暇や特別休暇、病気休暇も取得可能です。また、育児休業制度も整っています。
社会貢献度が高い
地方公務員の仕事は、地域や地域住民のために行うので、社会貢献度が高いといえるでしょう。民間企業とは異なり、地方公務員は人の生活に欠かせないインフラをスムーズに形成できるのが特徴です。
また、一方の地方自治体においては、公共性の高い事業を優先し、長期間に渡り行うことも可能です。
仕事が続けやすい環境
育児休業の取得率や復帰率が高く、仕事と育児を両立しやすいというメリットがあります。さらに、民間企業のように業績によって倒産したり、解雇されたりするリスクがないので、安心して働き続けることが可能です。
地方公務員の場合、他の都道府県に異動となることもほぼありません。
地方公務員にふさわしい人・適正
どのような仕事にも向き不向きがあるものです。
ここからは、地方公務員に向いている人の特徴について、いくつか紹介していきます。自身の特性と照らし合わせて、地方公務員を仕事として選択するかどうかを考えてみましょう。
地域に貢献したい人
社会貢献したいと考えている人には、地方公務員の仕事への適性があります。公共性の高い事業に関わることが多いため、社会に寄与しているという手応えを感じられるでしょう。
また、都市計画やインフラ整備、福祉サービスの提供などにも、直接取り組めます。
住人と近い距離で仕事がしたい人
地方公務員の中でも特に市町村職員は、地域住民と密に接する機会が多くあります。そのため、住民に寄り添った仕事がしたいという気持ちが大切になるでしょう。
住民の困り事や要望に真摯に耳を傾け、解決策を模索することにやりがいを感じる人が地方公務員に向いている可能性があります。
作業をコツコツと取り組める人
地方公務員の仕事は、地味なものや時間をじっくりと掛けて成果をあげるものも多くあります。即効性を求めることに特化した民間企業ではできない仕事です。
すぐに成果が出なくても、コツコツと地道に目の前の仕事に取り組める人は、地方公務員に適性があるでしょう。
ライフワークバランスを重視する人
地方公務員は、有給休暇や育児休業など与えられた権利を消費することに対して、積極的な職業です。手厚い福利厚生と組み合わせて利用することもできます。
そのため、ワークバランスを重視する人にとっては働きやすい職業だといえるでしょう。
地方公務員の年収・給与
ここでは全地方公共団体職員の平均給料月額についてみていきましょう。
総務省の資料「令和4年 地方公務員給与の実態」によると、平均給料月額は約30万円から約65万円となっています。そのため、地方公務員の年収は約600万円以上といえるでしょう。
地方公務員の将来性
地方公共団体と民間企業が連携して解決していかなければならない課題が多くあります。例えば、少子高齢化対策やSDGs関連の取り組み、外国人観光客の誘致およびオーバーツーリズム対策などです。
このような取り組みには、地域の発展や振興に対して情熱を持ち柔軟な発想力で、挑戦できる人材が必要になります。
まとめ
地方公務員の仕事は地域住民との密な関わりが基本になります。地域への愛情があり、なおかつ人とのコミュニケーションが得意な人や、困っている人の手助けをしたい人などに向いている仕事でしょう。
地方公務員の仕事は多岐にわたります。まずは、どのような分野を目指すのかという目標を定めてから、効率よく勉強をすすめていきましょう。