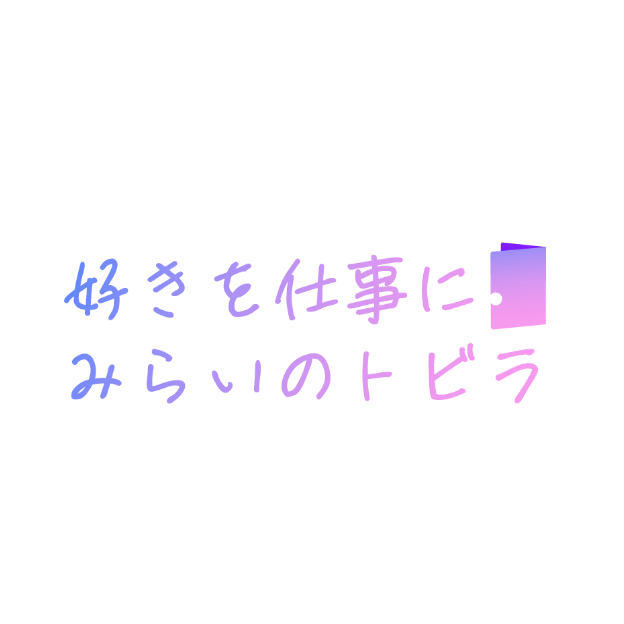通訳
通訳という仕事について、翻訳者との違いや働き方、スキルなどのポイントで解説します。普段は見えない通訳という仕事の現場まで学べます。「なりたい自分」になるための第一歩を踏み出しましょう。
通訳者の仕事内容とは?翻訳者との違い
通訳者と翻訳者は、言語を扱う専門職ですが、その仕事内容と求められるスキルには大きな違いがあります。通訳者は会話内容などの音声情報をリアルタイムで別の言語に翻訳します。即時性とコミュニケーションの理解が優先されるのが特徴です。話し言葉の特性を捉え、瞬時に反応する能力が求められるでしょう。これに対し、翻訳者は本や議事録などの文書を別の言語に翻訳します。即時性よりも高度な正確性と文脈への深い理解が要求されます。各言語の文化的な背景に基づいて精密な解釈を行うことも大切です。
コミュニケーションの場に立ち合って円滑な会話をサポートするか、文章とじっくり向き合って高い精度の訳文を作り上げるか。2つの仕事にはアプローチに大きな違いがあります。自分はどちらが向いているか、よく考えてみましょう。

通訳の主な3方式
同時通訳
同時通訳は、通訳者が発言者の話を聞きながらほぼリアルタイムで別の言語に訳し、マイクを通じて即座に伝える高度な通訳手法です。この作業は話を聞き、理解し、翻訳し、伝えるという複数のプロセスを同時に行います。そのため、極めて高い集中力と瞬時の判断力が求められます。大規模な国際会議や速やかな意思疎通が必要な場面で重宝されます。
逐次通訳
逐次通訳は、発言者が数文話した後に通訳者が話した内容を訳す通訳方法です。このプロセスを繰り返し、通訳者はより正確に理解しやすく情報を伝えます。同時通訳に比べると、タイムラグが生じ、会議などの時間は倍になる可能性があります。しかし、内容の精度を高めたい場面では適しています。
商談や会議、専門家との意見交換、インタビューなど、さまざまな場面で活用される通訳方式です。特に内容を正確に伝えることが重要な場合に有効です。
ウィスパリング通訳
ウィスパリング通訳は同時通訳の一種です。話し手の言葉を聞き手の耳元でささやくように通訳を行います。専用機材は不要で、話し手の言葉をリアルタイムで訳すため、スムーズに会話できるというメリットがあります。
向いている場面は1対1の対話や少人数の会議・商談、単独インタビューなど。少人数の場で用いられることの多い方法です。

通訳者の働き方
通訳者は、企業に所属する社内通訳者と、フリーランスに分かれます。
社内通訳者は日常的に通訳が必要な企業に勤務し、打ち合わせに同席して通訳します。出張やイベントに同行することもあります。
対してフリーランスは依頼に応じて柔軟に活動します。派遣会社に登録して案件を受ける人や、個人事業主として活動する人が多く、自分のペースに合わせて依頼を受けることが可能です。
どちらの場合も、事前準備が欠かせません。例えば講演の通訳を行う場合は、あらかじめ講演テーマについて学び、頻出すると思われる単語を知っておくことで、より正確でスムーズな通訳ができます。
また、スキルを磨くためにまずは社内通訳者として経験を積み、フリーランスへ転身する通訳者も多いのがこの仕事の特徴です。

通訳者に有効な資格やスキル
語学力が最も重要である通訳者は、必須となる資格はありません。しかし語学力を測るTOEICや実用英語技能検定を受験し、レベルを確認することが役立ちます。特に通訳志望者にはビジネス通訳検定(TOBIS)がおすすめです。
求められるスキルとしてまず挙げられるのがコミュニケーション能力。話者の意図を正確に理解し、適切に伝える力です。また、専門分野の知識を学び続ける姿勢も重要になります。専門用語に臆さず正確な通訳を行うことが、プロの通訳者に求められるからです。大学や養成学校で学ぶだけでなく、ボランティアで実務経験を積むのもいいでしょう。通訳者としてのキャリアを構築するためには、検定試験の合格だけでなく、幅広いスキルや経験を身につけることが大切であると言えます。
通訳者になるには
前述の通り、通訳者に必須の資格はありません。しかし高い語学力とコミュニケーション能力、幅広い教養、学び続ける姿勢が必要です。そのため、これらを育むために語学系学部のある大学に進学したり、通訳専門コースのある外国語学校に入学する人がほとんどです。また、聞き取った内容を瞬時に訳して伝えるなどの特殊な技術を学ぶ目的で、通訳あっせん企業が主催する教室などに通う人も大勢います。
さらに、教室では触れることの難しいネイティブ独特の言い回しやスラングを身につけるため、留学をする人もいます。
まとめ
グローバル化が進む現代社会。通訳は、異なる言葉を話す人同士の円滑なコミュニケーションを支える、重要な役割を果たす仕事です。これからもますますニーズが高まっていくでしょう。