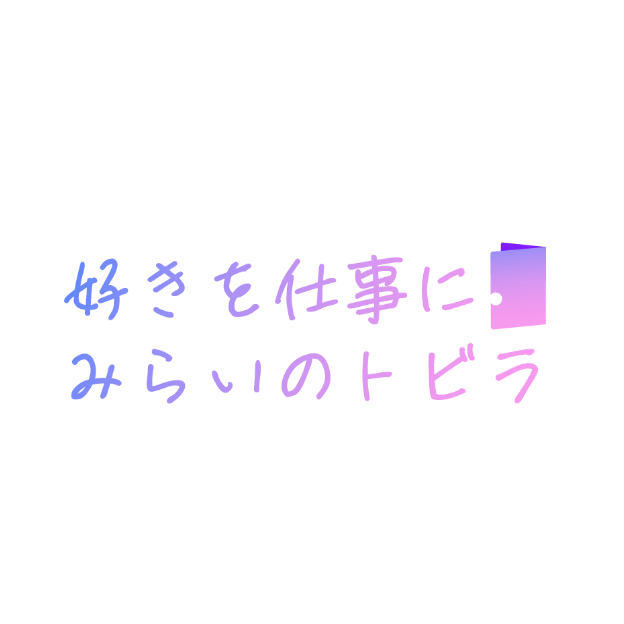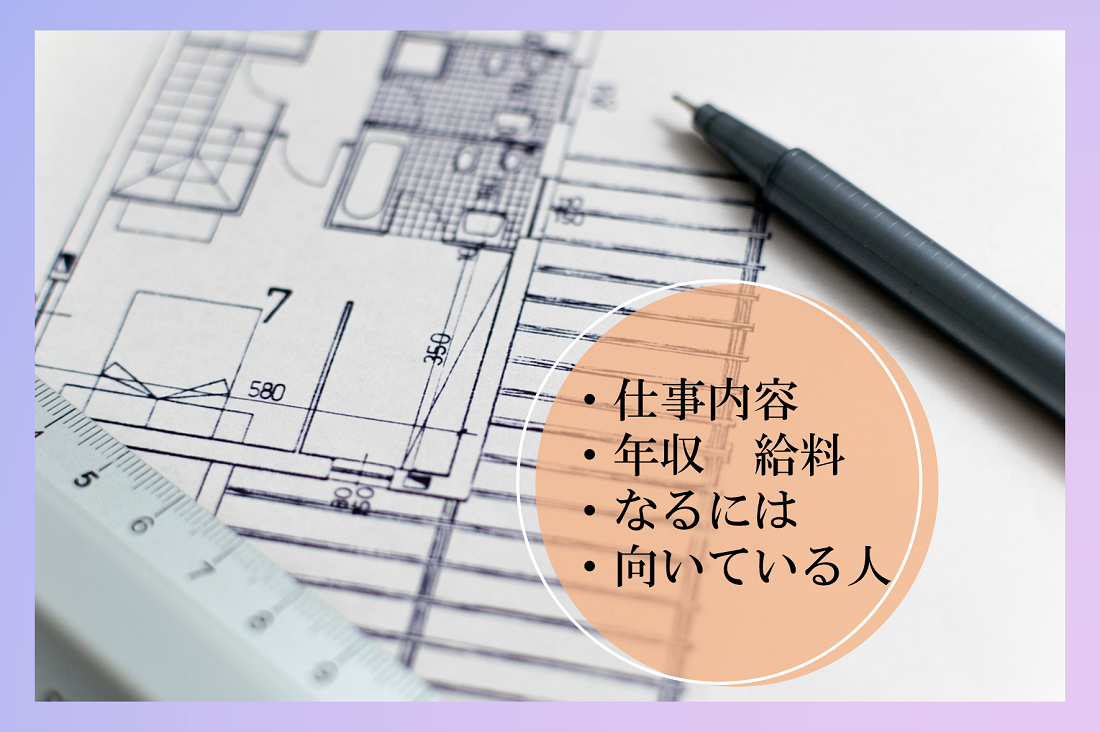
建築士
建築士という仕事について、仕事内容・なるには・やりがいなどのポイントで解説します。
建築士や建築関係、デザインの仕事に興味がある方はぜひこちらの記事をご覧ください!
【目次】
建築士には種類がある?

「建築士」とは「建築士法」に定められている資格を保有し、建築物の設計や工事監理などを行う人のことです。
たとえば、学校や病院、デパートやビルといった建物は、建築士によって設計され、その設計図を元に実際の工事現場で作業員を指揮したり、監督したりしています。
そのような建築士には、保有する資格によって3つの種類に職種が分かれます。
一級建築士
「一級建築士」は、一級建築士試験に合格した人のことです。国土交通大臣の免許を得て、どのような建築物でも設計や工事監理等を行うことができます。
たとえば、一定以上の高さのある建築物や、鉄筋コンクリート造や鉄骨造で大きな建築物は、一級建築士だけが設計や工事監理できます。
一級建築士試験の受験には、高等専門学校や大学、短期大学の卒業、二級建築士免許や建築設備士などの資格が必要です。
二級建築士
「二級建築士」は、都道府県知事の免許を得て、建築物の設計や工事監理を行う人です。一級建築士と比較すると、二級建築士が設計や工事監理できる建築物は制限されます。主に、戸建て住宅などの建築に携わるでしょう。
二級建築士試験を受験するには、高校や高等専門学校、大学や短期大学を卒業し、指定科目を履修済であることや、7年以上の実務経験が必要です。
木造建築士
「木造建築士」は、都道府県知事からの免許を受けて、2階建てまでの木造の建築物の設計、工事監理等を行える人のことです。木造建築士は木造の建築物について、高い専門性を持っています。
しかし、木造でも延べ面積が300平方メートル以上になると、木造建築士には担当できません。
木造建築士試験を受験する際は、二級建築士と同様の、学歴や実務経験が求められます。
建築士の種類による違いを簡単に解説

建築士は、何の建築士かによって、担当できる建築物の範囲が大きく異なります。
木造建築士は、木造かつ2階建て以下の建築物しか担当できません。このため建築物の約75%は、二級建築士以上でないと担当できないでしょう。さらに、一級建築士のみが設計、工事監理等ができる建築物は、全体の約半分にもなります。
建築士として働きたい場合、二級建築士以上の資格があった方がよいでしょう。
建築士の仕事内容

建築士はさまざまな人からの依頼を受け、建物を設計し、現場指揮や監督をしながら建築物の完成を目指します。
ここでは建築士の仕事について、施主の依頼から建物の完成までの流れを紹介します。実際の建築士が、どのような仕事をしているか確認していきましょう。
ヒアリングと打ち合わせ
施主から建築の依頼を受けた後、施主へのヒアリングを行い、建物のデザインや部屋数などへの要望、部屋の広さや予算などを打ち合わせします。
ここで施主から十分にヒアリングが行えていないと、施主の要望に沿わない建物が完成する可能性があるため、ヒアリングは非常に重要です。
建物の設計作業
施主との打ち合わせで、ある程度建物のイメージが固まった後は、建物の図面の作成に入ります。
設計作業にあたっては、設計ソフトを使ったり手描きしたりします。場合によっては、模型を作ることもあるでしょう。デザインだけでなく住む人の居心地や人の動線を考えながら、階段の場所等も決めて、設計図を完成させます。
工事現場の監視・監理
建築士は、設計図通りに建物が設計できるように、建築現場にも入って監視や監理を行います。
建築士は工事担当者と打ち合わせを行い、予定した通りの建材が揃っているか、設計図通りに工事が行われているかの確認が必要です。設計図通りでなければ指摘し、設計図通りになるよう求める責務を負います。
関連する事務作業
建築士は建設許可や道路の使用許可の申請、施主と施工業者との契約内容を折衝したり監修したりなどの、事務作業も行います。
建物が完成したら、最終チェックをしてから施主の立ち合いの元でもチェックし、施主から料金が支払われた後に、引き渡しまで行うのも建築士の仕事です。
建築士の働き方

ここからは、建築士として活躍できる就職先の働き方を紹介します。
建築士は基本的には、建築関係の仕事に就くことになるでしょう。たとえば、建物の建築を請け負う会社や、建物の設計を請け負っている会社などが候補になります。また、一見すると建築とはあまり関係のないような就職先もあります。
建築設計事務所
建築物の企画や設計、監理などを行います。
建築設計事務所と一口に言っても、デザイン性を重視している個人事務所や、全国で幅広く仕事している大手設計事務所があるなど、得意分野が異なります。
建築設計事務所へ就職したい場合は、それぞれの特色を理解した上で選ぶとよいでしょう。
建築会社
建築士として就職すると、建築物の建築計画や工事監理などを全体的に行います。建設会社は、建築士にとってポピュラーな就職先です。
建築会社で働くことで、あらゆる建設業界のノウハウを身に付けられるでしょう。しかしその一方で、建築会社に就職したとしてもすぐに一線で活躍するのは難しいという面もあります。
建築会社で、自身が建築士としてやりたいことを行えるかどうかの見極めが大事です。
ハウスメーカー
戸建て住宅の設計に特化している会社です。
ハウスメーカーで建築士として働くと、戸建て住宅を中心とした企画や設計、販売することが仕事になるでしょう。建築士として現場での業務についたり、事務作業したりするなど、さまざまな業務を経験できることが特徴です。
地方自治体の公務員
建築士は、地方自治体の職員として働く場合もあります。
公務員となった建築士は、県庁や市役所に務めながら、建築指導や都市計画、公共建築工事や住宅関係などの仕事に携われるでしょう。耐震診断や空き家対策、都市の再開発計画など、比較的規模の大きな仕事に関わることが特徴です。
不動産会社
建築士が不動産会社に就職した場合は、アドバイザーとしての活躍が期待されます。投資案件について、建築士として専門的な視点からのアドバイスが求められるでしょう。
また、投資案件の設計事務所や、施工会社の選定に携わることもあります。
独立して自営
建築士の資格を得て、ある程度の経験や実績を積んだ後は、独立することも可能です。
建築士として独立すれば、どのような仕事をするかを自分で決めることができます。頑張り次第では、年収が増える可能性もあるでしょう。
独立する場合は経営スキルも求められるため、しっかり準備することが大切です。
建築士になるには?

建築士になるための方法として、必要な学歴や実務経験などについて紹介します。
建築士を目指す人は、一級建築士や二級建築士、木造建築士などの資格を取得する必要があります。また、それぞれの建築士試験では受験資格だけでなく、免許登録にも要件があることに注意しましょう。
大学や専門学校に通う
一級建築士や二級建築士の資格取得に向けて、受験資格の要件を満たせるように、大学や専門学校で指定科目を履修しましょう。
大学では建築学部や理工学部の建築学科、芸術学部のデザイン学科やインテリア学科などが対象になります。専門学校や高等専門学校の場合は、土木工学科等が対象です。
大学や短大で指定科目を履修することで、二級建築士や木造建築士の受験資格を得られるでしょう。
実績を積む
すでに社会人になっている人の場合は、実務経験を積んで建築士を目指すことも可能です。
社会人として設計事務所等で7年以上働き、実務経験を積むことで、二級建築士や木造建築士の受験資格を得られます。二級建築士試験に合格し免許を登録すると、一級建築士試験を受験できるようになります。
実務経験で試験を受けられるため、大学や専門学校に通う必要がないことがメリットです。
建築士に向いている人の特徴

建築士になりたいけれど、自分が向いているかどうか分からないという人もいるでしょう。
ここからは、建築士に向いてる人によく共通している特徴について紹介します。全ての特徴を満たす必要はありませんが、あてはまる特徴が1つでもあれば、建築士として向いている可能性があります。
モノづくりに熱意がある
日頃からデザインや工作、DIYなどで何かを作ることを楽しんでいる人は、建築士として向いています。
建築士は建築物を設計し、完成させる職業ですが、仕事で求められる知識はとても多く、残業が発生するハードな仕事であるためです。
モノづくりが好きな人であれば、困難なことにもやりがいを感じて、乗り越えていける可能性があります。
創造力が豊かである
建築士は施主の要望をヒアリングし、予算内で施主の要望に沿った建物を建築する必要があるため、創造力の豊かさが必要です。
たとえば、建物の設計をする際には建物の外観や内装について考え、クライアントに喜んでもらえるように、アイデアをふくらませる必要があるためです。
デザインすることが得意である
建築士には外観と内装、建物の形状や色、照明などのデザインを行う業務があるため、デザインすることが得意な人が向いているでしょう。
建築士は建築基準や構造的な要件など、さまざまな条件がある中で、個性ある新たなアイデアを生み出し、形にしていく必要があります。
建築士の給料
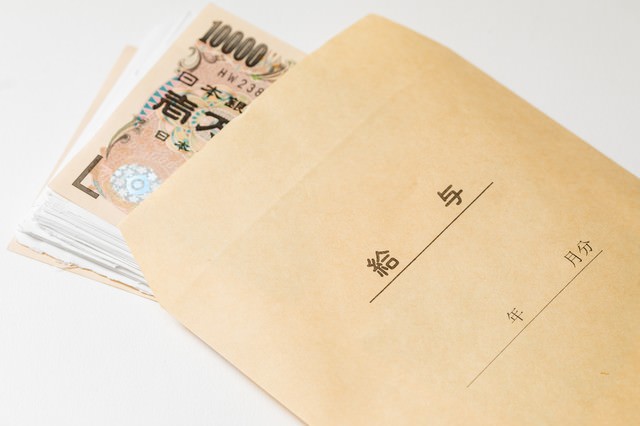
政府の資料によると、2019年の一級建築士の平均年収は約703万円です。二級建築士や木造建築士の給料についてはおおよそ、二級建築士は約500万円、木造建築士は350万円~400万円といわれています。
給料は一級建築士がもっとも多く、次いで二級建築士、木造建築士になるでしょう。
建築士のやりがい

建築士は、人の住む住宅や街で利用される建物などの建築に携わる職業です。
自分たちが関わった建物を利用する人々や人の笑顔を見て、やりがいを感じられるでしょう。また、何もなかった土地に建物を建てて完成すると、ゼロの状態から作り上げたという達成感も得られます。
まとめ

人が生活する上で欠かせない建築士の役割は、今後も必要とされることでしょう。不動産業界では特に、投資案件が増えていることから、建築士の需要が高まってきている状況です。
しかし、建築士になるためには建築士試験に合格しなければならず、建築士試験の受験には、学歴や実務経験の要件を満たす必要があります。
自身がどのように資格取得を目指すかを考え、建築士になるための道を進んでいきましょう。