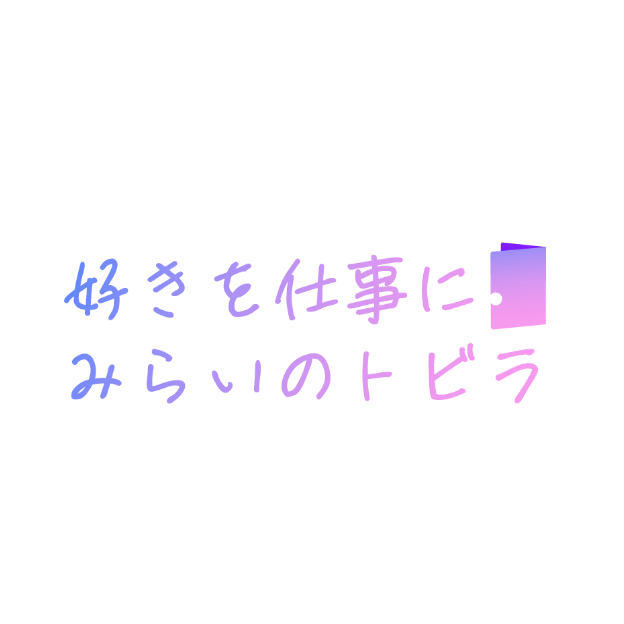農業の仕事内容についてわかる!必要な知識や就職先まで解説
農業とは具体的にどのような仕事をしているか、ご存じでしょうか。この記事では農業の仕事の内容や経験・年齢の条件は関係あるか、農業を行うために必要となる知識などを紹介しています。農業に興味のある人や、人に喜ばれる仕事をしたい場合はぜひ、こちらを読んでみてください。
【目次】
農業って何をするの?
農業とは、自然環境を利用して農産物を生産し、出荷することで利益を得る産業のことです。人が生活していく上で食事は欠かせないものですが、農業はその食事に必要な食料供給を担う重要な産業になります。
また、それ以外にも、地域の環境保全や地方活性化の役割も担っており、地域貢献にも役立っている産業です。
農業の仕事内容
農業の主な仕事は、その土地の自然環境を利用した農産物の生産です。育てる農産物に適した土づくりをして肥料を加え、病害虫対策等の手入れをしながら収穫の時期を迎えます。
自然の中で農産物を育てるため、自然との関わりが深いことが農業の特徴です。ただし、天候が農産物のできに影響を与えることもあるので、想定した通りに農産物が育たない可能性はあります。
しかし、農業は苦労して育てた農産物を収穫する達成感や、自ら収穫した農産物が消費者に喜ばれることでやりがいを感じられる仕事でしょう。
未経験から農業を始めることはできる?
未経験から農業を始めるというのは、難しい挑戦です。しかし農地の確保や資金、同地域で農業をする人たちとの、人間関係などを良好に保てるならば可能でしょう。
農業を始めたい場合は、まず農地を確保しなければなりません。しかし、日本には「農地法」という法律があり、農地または採草放牧地を買ったり借りたりする際には「農業委員会」の許可が必要です。農業委員会では、農地法に関する事務処理を行っています。
また、農地の確保だけでなく様々な農機具、苗などを揃えるためには、ある程度のまとまった資金が必要です。資金繰りが難しい場合は、補助金制度の利用を検討してみましょう。
農業を始めるにあたり、就農予定地域のプロ農家で研修を受けると、熟練の方から有益な知識や技術を学ぶことができるでしょう。加えて、地域の人たちと信頼関係を築くために、積極的にイベントごとへ参加してみることをおすすめします。
農業に年齢は関係ある?
厚生労働省の「令和3年新規就農者調査結果の概要」によると、令和3年の農業への新規参入者約3,800人のうち、49歳以下は約2,690人と7割程度でした。農業への新規参入者のうち、3割程度は50歳以上で始めていることになります。
したがって、農業は何歳からでも始められる仕事といえるでしょう。
農業を始める際に必要な知識
農業を始めるためにはどのようなことを知っておかなければならないか、必要になる知識を紹介します。
農業はすぐに始められる仕事のように見えて、実際には様々な手続きや費用などがかかる仕事です。農業を始めたいと考えている場合は、こちらを参考に準備しておきましょう。
農業を始める際にかかる費用
いちから農業を始めたい場合は、起業のための資金として、一般的に570万円程度の資金が必要になります。
農業を始める際に必要となる農地の確保や、農作業で必要になる機械、施設などを用意するための費用です。他に、農地に植えるための種苗や肥料、機械等を動かすための燃料などの費用も必要になります。
しかし、資金をすべて自己資金で用意する必要はありません。自治体の補助金や、借入金で賄うことも可能なため、必要な自己資金の目安は230万円程度になるでしょう。
農業に対する補助金制度について
新規就農者向けの補助金・助成金としては、以下2つの制度を利用できる可能性があります。
・就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)
・経営発展支援事業
「就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)」は、就農前の研修や就農直後に経営確立するための資金交付制度です。原則49歳以下等の要件を満たすことで、就農準備資金は年間最大150万円を最長2年間、経営開始資金は年間150万円を最大3年間受けられます。
「経営発展支援事業」は、就農後に機械・施設等の導入を都道府県が支援した場合、国がその支援額の2倍を支援する制度です。支援対象となる機械・施設等導入にかかる経費の上限は、1,000万円になります。(経営開始資金交付対象者であれば上限500万円までに制限)
どちらの制度も要件が細かく設定されているため、利用したい場合は、要件をしっかり確認しておきましょう。
農地を確保する方法
農地を新たに確保したい場合は、農地法に基づいて、農業委員会の許可が必要です。もし、個人で農地を確保したい場合に、許可を得るには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。
・農地のすべてを効率的に利用できる営農計画がある
・農作業に常時従事できる(原則:年間150日以上)
・周辺での農地利用に支障を与えないこと
これらの他に、下限面積要件(農地として経営する面積)を設けている自治体もあります。
農業で働くには
農業で働いていくには、将来的に失敗することがないよう、農業に関する豊富な知識や技術を身に付けることが必要です。
ここからは、農業の知識や技術を学ぶ方法を2つ紹介します。今後農業に携わることを考えている人は、いずれかの方法で農業の知識や技術を身に付けていきましょう。
農業の技術を学べる学校に通う
農業の専門的な知識を得たい場合や、体系的に学びたい場合は、農業全般のノウハウを学べる大学や、専門学校に通うことを検討してみましょう。
学校では、農業概論や農業生産学といった農業に必須な知識を学べます。また、将来独立して働きたい場合には、農業経営学や農業簿記なども学んでおくと役に立つでしょう。
各都道府県の農業大学校であれば、夜間や週末のみのコースが存在する学校もあるので、日中働きながら学ぶことも可能です。すぐに農家になることが難しい場合は、まず学校で学んでみましょう。
農家に弟子入りをする
すぐにも農業に携わりたい場合は、農家に弟子入りする方法もあります。
自分が栽培したい農作物を生産している農家に弟子入りできれば、費用をかけることなく、必要な知識や技術を身に付けられることがメリットです。
また、農家に弟子入りすることでプロの農家の人から、自身が新規就農する際のアドバイスをもらうことも可能でしょう。
農業の就職先
農業で働くためには、どのようなところへ就職すればよいかについて紹介します。
農業は個人で始めることもできますが、農業を営んでいる法人へ就職して農業に携わるという方法も一つの手です。以下を参考に、どのような働き方が自分に向いているかを考えてみましょう。
農業法人
「農業法人」は大規模農業をしています。農業について大学や専門学校で学んだ人が、目指す就職先になることが多いでしょう。
最初から設備や道具の整った環境で農業することで、更に有用な知識や技術を身に付けやすくなっています。また、農業に年齢は関係ないため、経験豊富なベテランから、様々な教えを受けられる機会もあるでしょう。
農業法人に就職した場合は「雇用就農」と呼ばれ、一般的な給与所得者と同じような労働形態になります。
自営農業
「自営農業」は家族で営んでいることがほとんどであり、忙しい時期だけ人を雇って働いてもらう形態であることが多いでしょう。また、実家が農業を営んでいた場合は、家族と一緒に働けば自営農業の形態になります。
小規模な経営なので、個に応じた丁寧な指導によって様々な知識や技術を身に付けていけることがメリットです。すでに農地や設備などがそろっていることも強みでしょう。
しかし、家族と農業に関する意見が合わないと、衝突が生じるリスクはあります。
企業の農業部門
現在は農業に参入している別業界の企業もあるため、そのような企業で働くことも選択肢に入れましょう。
農業部門を設けている企業には、スーパーマーケットを全国展開している企業や、観光と農業を結びつける取り組みを行う大手旅行会社、調理家電を販売する大手家電メーカーなどがあります。
他にも農業に参入している有名企業があるので、社内からのバックアップを受けつつ農業に携わりたい人は、該当の企業へ就職を目指すとよいでしょう。
独立開業
新たな農家として「独立開業」することも検討してみましょう。
農業は人の生活に欠かせない産業であるため、新しく農業を始める人に対応した補助金制度が用意されています。自分で農地を確保し、機械等の設備を整えていくのは大変ですが、補助金制度の要件を満たしていれば、様々な補助金の交付を受けられるでしょう。
農業法人や企業の農業部門などで、十分キャリアを積んだ後に補助金を活用し、独立開業を考えるのもおすすめです。
まとめ
後継者不足が危ぶまれている農業ですが、人の生活に必要な産業です。人が生きていく上で、食事が必要なくなることはないので、今後も重要視されることは変わらないでしょう。
新規就農者に対しては補助金制度が存在するため、自己資金が少なくても農業で独立開業することは可能です。最初から独立してやっていくことが難しい場合は、企業の農業部門や農業法人に入り、知識や技術を身に付けてから独立していってもよいでしょう。
将来農業に携わりたい人は、必要な知識や技術をどのように身に付けていくか考え、進路や就職先を検討してみましょう。