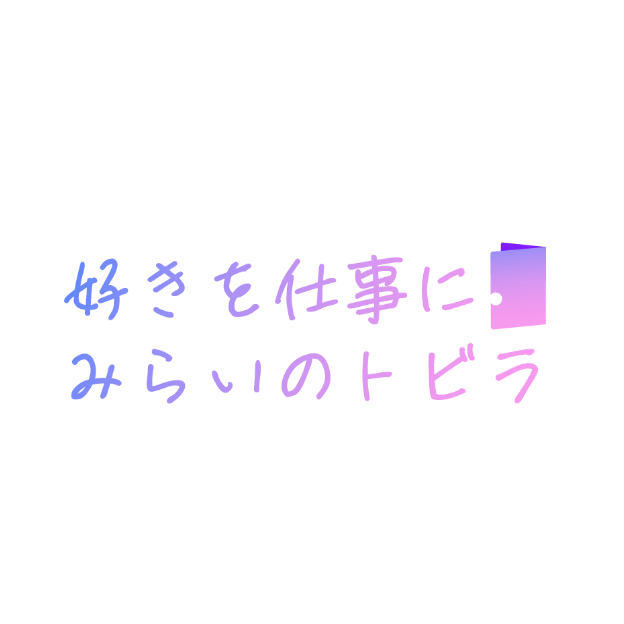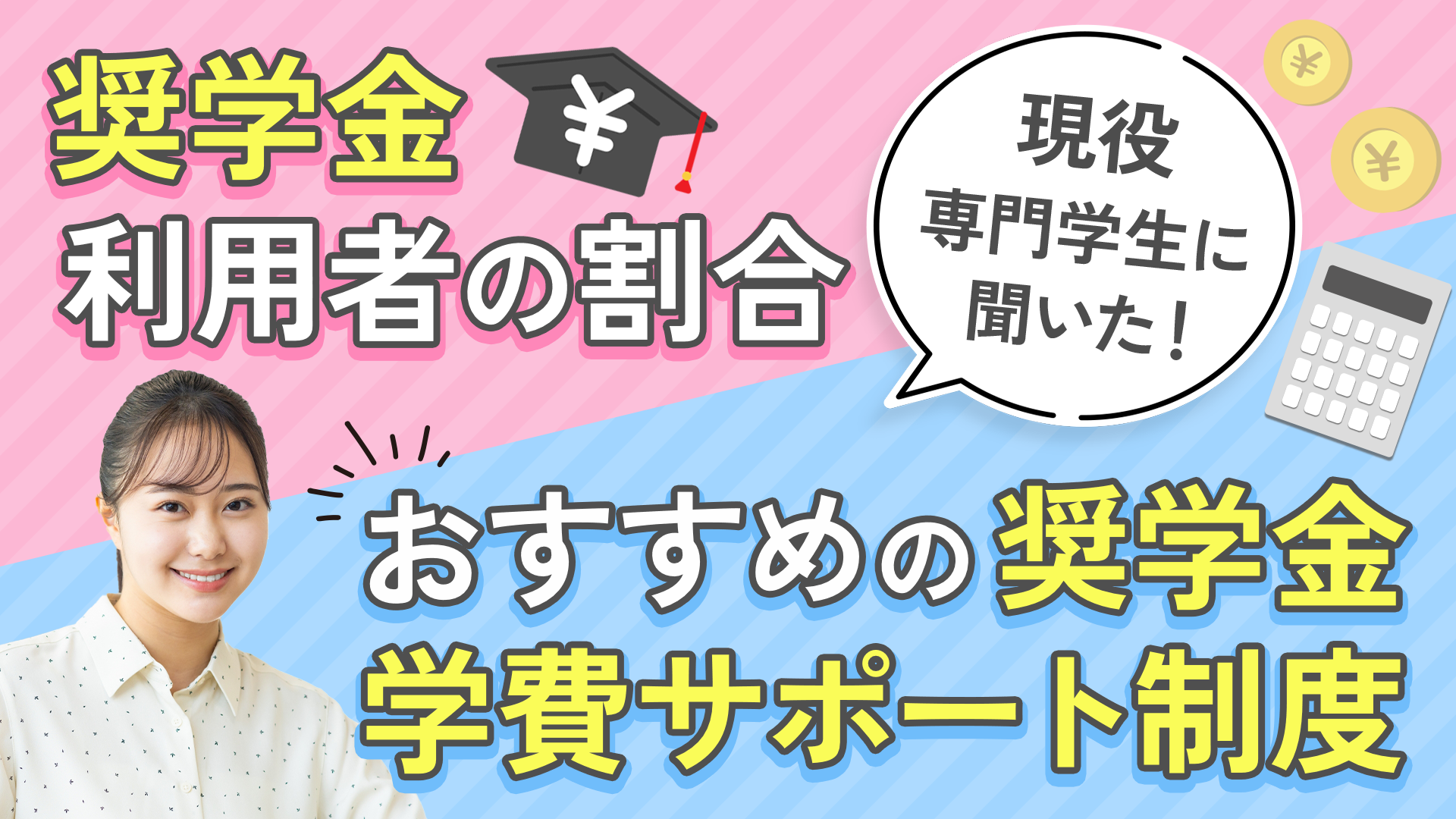
【現役専門学生に聞いた!】奨学金利用者の割合&おすすめの奨学金・学費サポート制度!

専門学校への進学を考えるにあたって、奨学金に興味があるものの、制度の具体的な内容まではよく知らないという方もいるでしょう。
この記事では、奨学金をはじめとする学費サポート制度の詳しい内容を紹介します。学費に関する心配を少しでも減らしたい人は、ぜひ本記事をチェックしてみてください。
【目次】
1.専門学校進学にかかる費用は?
専門学校の学費には、通常の授業料のほか、入学金、授業料、実習費、設備費などが含まれます。
在学中にかかる学費の相場は約190万円~約450万円で、1年次に入学金を含むすべての費用、2年次では入学金を除く費用を支払うのが一般的です。
金額に開きがあるのは、分野や修業年数によって学費が変わるためです。特に、分野による違いが出やすいのは実習費でしょう。
たとえば、製菓や調理関係の学校は、実習が多く設備も高額なため、実習費も高い傾向にあります。一方、簿記など商業実務関係の学校は実践教育が主となるため、実習費は安く済むでしょう。
修業年数による学費の違いについては、3年制の専門学校の場合、2年制に比べて1年分多くなります。
2.奨学金制度を利用している学生の割合
では、実際に奨学金制度を利用している人はどのくらいいるのでしょうか。
三幸学園の専門学生対象のアンケート調査では、約47%の人が奨学金制度を利用していると回答しています。ほかには、途中で利用をやめた人や、今後利用予定だと答える人もいました。
このアンケートから、およそ2人に1人が奨学金を利用していることが分かります。
3.利用者数が多い奨学金制度
ここからは、具体的な奨学金制度について取り上げていきます。まずは、多くの人に利用されている奨学金制度の紹介です。
3-1.日本学生支援機構給付奨学金
日本学生支援機構の「給付奨学金」は、返済する必要がない奨学金です。世帯収入が基準に当てはまり、高校時代の成績が良く、進学先でしっかりと学ぶ意欲を持っている学生であれば、給付奨学金に申し込めます。
成績の基準は、高校1年次からの評定平均値が5段階評価で3.5以上です。学ぶ意欲については、自身が通う高等学校による判断となります。方法としては、面談の実施やレポートの提出などを行う学校が多いでしょう。
なお、給付奨学金の場合、全員が共通の固定支給額ではありません。世帯収入以外にも、志望先が国公立か私立か、自宅通学か自宅外通学かなどの条件によって、給付額が異なることを知っておきましょう。
3-2.日本学生支援機構貸与奨学金
日本学生支援機構の「貸与奨学金」は、返済を前提とした奨学金です。進学のために学費を借りることになるため、この奨学金を利用する際は、返済時の利息を考える必要があるでしょう。
貸与奨学金には、利息がつかない第一種奨学金と、利息がつく第二種奨学金の2種類があります。
この奨学金に申し込めるのは、世帯収入や高校時代の成績が基準に当てはまる学生です。なお、成績の基準は、以下のように第一種・第二種で異なります。
・第一種:5段階評価で3.5以上
・第二種:平均水準以上
貸与額については、複数の選択肢から希望の金額を選ぶことが可能です。ただし、世帯収入によっては、貸与額が制限される場合もあります。
貸与された奨学金は、貸与終了月翌月から数えて7か月後に返済開始となります。たとえば、3月の卒業月まで貸与を受けた場合、10月が初回の返済月です。
3-3.地方公共団体の奨学金
進学のための奨学金については、地方公共団体が設ける制度を利用することも可能です。
本人や保護者が、その自治体の居住者または出身者で、家計や学力など自治体が定める基準を満たす場合に、奨学金制度を利用できます。
地方公共団体の奨学金は、大まかに以下の3種類に分けられます。
・給付型奨学金:返済不要
・貸与型奨学金:無利子
・貸与型奨学金:有利子
奨学金の種類は自治体によりさまざまですが、無利子タイプの奨学金が多く、有利子タイプでも利息は低めに設定されています。
そのほか、看護師や理学療法士などの医療系国家資格の取得を目指す学生を対象に、「貸与型奨学金」を用意している自治体もあります。このタイプの奨学金の特徴は、卒業後にその自治体で一定期間医療業務に従事すると、返済免除になるという点です。
3-4.教育訓練給付金
「教育訓練給付金」とは、厚生労働省の「教育訓練給付制度」に基づく奨学金です。
この給付金は、働く人のキャリアアップ促進を目的としたもので、雇用保険の加入期間が一定以上ある人が給付の対象となります。
この制度では、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講する必要がありますが、修了後には費用の一部が給付金として支給されるため、最終的な負担を抑えることが可能です。
対象となる教育訓練はレベル別に3種類あり、受講費用の給付率はそれぞれ異なります。
4.専門学生がおすすめする奨学金・サイト
次に、多くの専門学校生がおすすめする奨学金制度やサイトを紹介します。
4-1.育英財団
「育英財団」とは、才能ある若者の修学を支援するために設立された財団の総称です。さまざまな育英財団が、優秀な人材の育成に貢献する取り組みの一環として、奨学金制度を用意しています。
奨学金の対象となるのは、成績が優秀で、行いが正しくあるにもかかわらず、経済的な事情で自ら学費を用意できない人です。審査を経て奨学生と認められた人には、学業に励むための資金が給付、あるいは貸与されます。
4-2.目指す職種別の奨学金
奨学金の中には、職業につながる資格取得を志す人を対象にしたものもあります。
この奨学金は、形式的には貸与型ですが、一定条件を満たすことで返済不要になるため、目指す職業が決まっている人におすすめです。
たとえば、東京都社会福祉協議会が実施する「保育士修学資金貸付制度」では、保育士養成施設で学び、卒業後に都内の保育所等で5年働くことで、返済が免除となります。
また、厚生労働省による「介護福祉士修学資金貸付」でも、厚生労働大臣の指定養成施設で学んだのち、介護福祉士として5年間介護業務に従事すれば、奨学金を返す必要がありません。
4-3.就職先企業による奨学金代理返済
日本学生支援機構の貸与奨学金を利用した人は、卒業後に働きながら奨学金を返済するのが一般的です。
しかし、学生の就職先企業が「奨学金返還支援(代理返還)制度」を利用している場合は、その限りではありません。
この制度では、就職先企業が直接、日本学生支援機構に奨学金の返還残額を送金するため、従業員個人の負担が軽減されます。
4-4.奨学金サイト「ガクシー」
奨学金制度には、「日本学生支援機構」のように比較的知名度の高いものだけでなく、地方自治体や公益財団法人による奨学金など、さまざまなものがあります。
多様な選択肢の中で、どのように奨学金制度を選べば良いか迷ったときは、「ガクシー」を利用してみるのも良いでしょう。
「ガクシー」は、奨学金制度の利用を検討している学生や保護者向けのウェブサイトです。
このサイトの特徴は、日本のほぼすべての奨学金制度を網羅していることです。数ある奨学金制度の中から、給付型や貸与型、職業特化型といったタイプ別に絞り込んで検索できるため、自分の状況に合う奨学金が見つかるでしょう。
また、入学時だけでなく、在学中でも申し込める奨学金制度を紹介しているのも、ガクシーの特徴です。
奨学金制度の探し方が分からないという人は、ぜひ一度サイトをチェックしてみてください。
参考サイト:https://gaxi.jp/
5.-番外編-進学先の学校独自の学費サポート制度

最後に、学費の支払いが困難な学生に向けた、専門学校独自の支援制度の例を紹介しましょう。
5-1.特待生制度
「特待生」とは、入試によって、学業面も人間性も優れていると認められた人の総称です。そして「特待生制度」とは、そのような学生が、金銭的な優遇を受けられる仕組みのことです。
一般的には、入試によって特待生としてのランクが決まり、ランクが上に行くほど、優遇を受けられる金額が高くなります。
特待生制度の主な内容としては、「入学金の減免」「授業料の減免」「奨学金の給付」といった項目が挙げられるでしょう。
また、特待生制度の利用期間については、在学期間中ずっと優遇を受けられるケースもあれば、1年ごとに審査されるケースもあります。
そのため、特待生制度の詳しい内容については、各学校の募集要項で確認することをおすすめします。
5-2.学費分割納入制度
日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けることを前提に、学費を月々分割で払える仕組みを導入している学校もあります。
この場合、日本学生支援機構から毎月貸与される奨学金が、毎月の学費支払いに充てられます。
授業料や施設設備費といった学費は、基本的に年1回または年2回での支払いとなりますが、分割納入制度を利用することで、まとめ払いによって生じる金銭的負担を和らげることが可能です。
別途事務手数料はかかりますが、利息なしで学費を分割払いにできる点は大きなメリットと言えるでしょう。
5-3.グループ校進学・グループ企業就職
運営母体が同じ複数の専門学校がある場合、そのグループ内で進学する人に向けた学費サポート制度が用意されていることがあります。
たとえば、グループ校卒業者・卒業見込者がグループ内の別の学校に入学する場合や、兄弟姉妹や親がグループ校の卒業生・在校生である場合に、入学金や学費を減免するという仕組みです。
また、複数社で構成される企業グループの中には、「奨学金返還支援」を導入している企業もあるため、奨学金をもとに進学した後は調べておくと良いでしょう。
こうした金銭的支援が行われている企業グループに就職すれば、借りた学費の返済負担を軽減することが可能です。
まとめ
本記事では、さまざまな種類の奨学金制度・学費サポート制度を紹介しました。奨学金の中には、世帯収入や成績によって利用の可否が決まるものもあるため、事前にしっかり把握しておくことが重要です。
また数年先のことも考え、進学後の学費支援制度や、企業の奨学金返還支援などについても調べておくと、奨学金の利用を安心して検討できるでしょう。
奨学金の利用を検討している人はこれらを踏まえ、自分に合った奨学金制度を探してみてください。